「ワーホリに行くために退職したいけど、いつ辞めるのが一番お金が残るの?」
「住民税が0円になるタイミングがあるって本当?」
これからワーホリ・留学で退職予定の会社員の方へ。
退職日を1日ズラすだけで、手取りが数十万円変わることをご存知でしょうか。
逆に言えば、何も知らずに会社に言われるがまま退職日を決めると、現地での生活費2〜3ヶ月分をドブに捨てることになります。
 Kea(ケア)
Kea(ケア)Kia ora!NZワーホリ準備中、現役SEのKeaです。
私自身、退職時に「いつ辞めるのが最強か?」を徹底的にシミュレーションしました。
この記事では、SEの私が導き出した「税金・社会保険・ボーナス」から見たワーホリ退職の最適なタイミングを、わかりやすく解説します。
結論:あなたの退職日は「この3パターン」から選べ
細かい計算は抜きにして、まずは結論です。
あなたの「ボーナス事情」と「リスク許容度」によって、最適解は以下の3つに分かれます。
【パターンA】ボーナスがない(少ない)人
最適解:12月31日 退職(年内出国)
→ 住民税(約10〜20万円)を0円にする「節税特化」ルート。
【パターンB】ボーナスがある & 減額リスクを回避したい人
最適解:ボーナス支給月の「翌月以降」の末日退職
→ 住民税は諦めて、ボーナス満額+給与を確実に確保する「安全策」ルート。
(例:12月ボーナスなら3月末退職、7月ボーナスなら8月末退職)
【パターンC】ボーナスがある & 会社との調整が可能人
最適解:12月30日 退職(年内出国)
→ 「住民税0円」+「ボーナス手取りアップ」を両取りする、理論上は最も手取りが最大化されるルート。
※ボーナス支給月に退職できる場合に限る。
パターンCが一番最強ですが、「退職申告は1ヶ月前」等のルールによりボーナス査定前に退職がバレて減額されるリスクがあります。
ご自身の会社の就業規則を確認し、Cが無理ならBを選ぶのをSEが推奨する退職戦略です。
ここからは、この結論になぜ至ったのか、3つのロジックを解説していきます。
ロジック1:住民税(約18万円)を消滅させる「1月1日ルール」
まず、手取りを増やす最大のハックが「住民税の課税タイミング」です。
住民税は、毎年「1月1日」に日本に住所がある人に対して、前年の年収分が課税されます。
逆に言えば、
いくら得するのか?(目安)
| あなたの年収 | 節税額(手元に残るお金) |
|---|---|
| 300万円 | 約12万円 |
| 400万円 | 約18万円 |
| 500万円 | 約24万円 |
12月31日までに退職し、海外転出届を出して出国すれば、この金額がまるまる浮きます。
ボーナスがないフリーランスや年俸制の方は、迷わずこの「年内脱出ルート」を選んでください。
なぜ「年末」が良いのか?
年の途中(6月や11月)で出国しても住民税は0円になりますが、その分「その年の年収」も低くなるため、節税できる金額(インパクト)が小さくなります。
「1年間フルで稼いで、その税金を全額チャラにする」ことができる12月末退職が、システム的に最もコスパが良い選択です。
ロジック2:住民税を払ってでも「時期をズラすべき」理由
「じゃあ全員12月末に辞めればいいじゃん!」と思いますよね。
しかし、ここには「ボーナス査定の罠」があります。
多くの会社のボーナスは「過去の成果」+「将来への期待値」で構成されています。
12月末退職のために11月に退職を申告すると、この「将来分」が0とみなされ、
【リスク】18万円の節税 vs 査定ダウン
年収400万円の場合、年内退職の節税メリットは約18万円でした。
しかし、もし会社に「辞めるならボーナスは2割カットね(将来分なし)」と判断されたらどうなるでしょうか?
12月退職は、「会社が減額してこないこと」ならば有効な手です。
対して、ボーナスをもらってから退職を切り出す(3月末退職)ルートは、安全策です。
これが、多くの会社員にとって「年明けまで待つ(3月末退職)」が正解になる理由です。
ロジック3:【超上級編】退職日は「30日」か「31日」か?
※この章は制度理解が前提となる上級者向けの内容です。
会社の就業規則・人事対応によっては実行できないケースもあります。
もしあなたが「ボーナス支給月に退職できる(パターンC)」という状況なら、最後の選択肢があります。
退職日を「末日の前日(30日)」にするか、「末日(31日)」にするかです。
結論、リスクを取ってでも手取りを最大化したいなら「30日退職」が理論上の最強手です。
最強コンボ:30日退職 + 末日出国
退職の際に社会保険いつまで使えるのでしょうか?
社会保険は「資格喪失日(退職日の翌日)」を基準に月単位で計算されるため、
退職日が月末か前日かで、社会保険料の扱いが大きく変わります。
「ボーナス月の30日に退職」し、かつ「その月の末日(31日)中に日本を出国」した場合、以下のスキームが成立します。
| 比較項目 | 12月31日退職(末日) | 12月30日退職(末日前日) +31日出国 |
|---|---|---|
| 12月給与の社保 | 会社と折半(天引き) | 0円(免除) |
| 冬ボーナスの社保 | 会社と折半(天引き) | 0円(免除) |
| 国民年金・国保 | 加入不要(会社健保) | 0円(加入義務なし※) |
| 医療保険の状態 | 31日まで会社健保が有効 (3割負担) | 31日は無保険 (10割負担のリスク) |
| 手取りの差 (年収400万試算) | 基準 | +数万円〜約10万円程度お得になる可能性あり(年収・ボーナス額・保険料率により異なる) |
【必須条件】12月28日までに役所へ行け!
この「冬の最強コンボ」を成功させるには、役所の営業日に注意が必要です。
通常、役所は12月29日〜1月3日が閉庁日(休み)になります。
そのため、必ず「年内の最終営業日(通常12月28日)」までに窓口へ行き、転出届を提出してください。
- 行く日: 12月28日以前(出国2週間前から可)
- 書く内容: 転出予定日を「12月31日」と記入
これで、「手続きは28日に完了しているが、効力は31日に発生する」という予約状態を作れます。
これを忘れると、1月4日まで手続きできず、住民税0円計画が全て破綻するので要注意です。
「冬」vs「夏」どっちのボーナスでやるべき?
このテクニックは、冬だけでなく「夏のボーナス(6月・7月など)」でも使えます。
むしろ、航空券が高騰し役所も閉まる「年末」よりも、夏の方が実行難易度は圧倒的に低いです。
しかし、「トータルの利益」で比較すると、やはり冬が最強になります。
- 夏のボーナス(6月30日出国)の場合:
社保免除(約10万)は成功しますが、住民税(約18万)は消せません。
(住民税は「1月1日」に日本にいた時点で、その年の課税が確定しているため)
- 冬のボーナス(12月31日出国)の場合:
社保免除(約10万)に加え、来年度の住民税(約18万)も消滅します。
合計で約28万円近い利益が出ます。
SEの結論
「実行のしやすさ(安全性)」なら夏、「利益の最大化」なら冬です。
冬にこのコンボを決めるには、「12月31日のフライト」と「事前の役所手続き」を完璧にこなす必要があり、さらに当日は無保険という綱渡りになります。
ご自身のリスク許容度に合わせて選択してください。
よくある質問(FAQ)
ここでは、退職日調整について特によくある疑問だけをまとめました。
- 12月31日退職で「出国」して住民税0円にするには?
-
年末に役所が開いている最終日(通常28日)までに手続きしてください。
海外転出届の「転出予定日」を「12月31日」と記入して提出し、実際に年内に出国すればOKです。
31日当日には役所に行けなくても、事前の手続きで「1月1日に日本にいない状態」は作れます。 - 30日退職の場合、会社に返金してもらうの?
-
ボーナス支給時にすでに社保が天引きされている場合、30日退職によって「引きすぎ」になります。
後日、会社から差額が返金されます(または最後の給与で調整)。
会社の人事に「同月得喪になるので調整お願いします」と伝えておくとスムーズです。 - 有給消化中は「在籍」扱い?いつ出国すればいい?
-
有給消化中も「在籍中」です。
例えば、最終出社日が12月15日で、12月31日まで有給消化する場合、退職日は「12月31日」となります。
この場合も、年内に海外転出届(予定日:12/31)を出して出国すれば、住民税0円は適用可能です。 - 退職日が月末前日の場合、健康保険はいつまで使えますか?
-
原則として「退職日まで」使えます。
会社の健康保険は、退職日の翌日に資格喪失となるため、
退職日が12月30日の場合、12月30日まで健康保険が有効です。12月31日は無保険状態になるので気をつけてください。
まとめ:自分の「損益分岐点」を見極めよう
ワーホリ退職の最適解まとめです。
- ボーナスが少ない人
→ 12月末日退職で「住民税」を消す - ボーナスが多い&減額回避したい人
→ 翌年3月末退職で「ボーナス満額」を確保 - 【最強】ボーナス月退職が可能な人
→ 「12月30日退職」で住民税0円&社保免除のダブル取り
このロジックを理解した上で行動すれば、無駄な税金や保険料を支払うリスクを大きく減らせます。
浮いたお金は、現地の美味しいコーヒーや旅行に使ってくださいね!
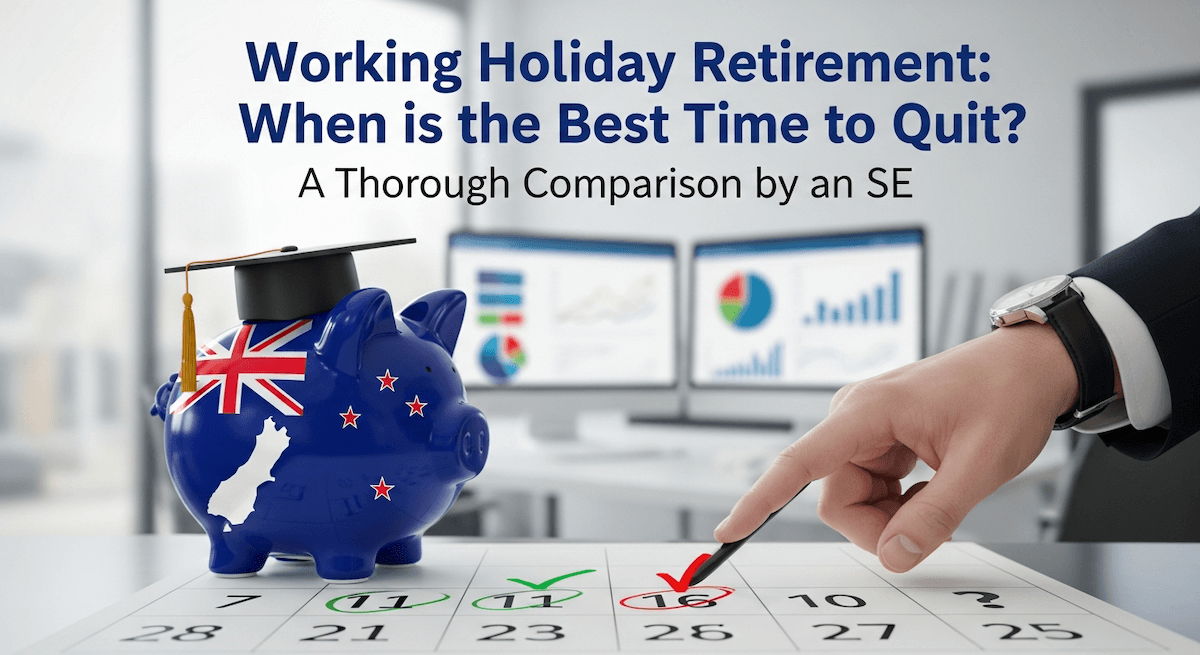
コメント