「ワーホリのために会社を辞めたいけど、税金や年金の手続きが複雑すぎて怖い…」
「30歳まで会社員だったけど、NISAや401k(企業型DC)はどうなるの?」
そんな不安を抱えている、30歳を目前にしたあなたへ。
 Kea(ケア)
Kea(ケア)Kia ora!「ふふろぐ」運営のKea(ケア)です。
私自身、30歳を機にIT企業を退職し、妻とNZワーホリに挑戦するまさに当事者です。
SE(システムエンジニア)という職業柄、曖昧な手続きは許せません。
そこで退職まわりの手続きをプロジェクト化し、すべて洗い出して「ToDoリスト化」しました。
この記事は、退職してワーホリに挑戦するアラサー会社員が直面する30歳会社員特有の資産(積立NISA・401k)の手続きまで網羅した、あなたのための【完全版】攻略ログです!
- 退職前から渡航後まで、やるべき全手続きの時系列マップ
- 「税金」「年金」「健康保険」「失業保険」で損しないための最適解
- 30代会社員が見落とす「積立NISA」「401k(iDeCo)」の落とし穴
- SE兼採用担当の私(と旅プロの妻)が実際にどう選択したか



私自身、積立NISA(ニーサ)や確定拠出年金を活用して資産形成をしていますが、ワーホリに行く時にどうすれば良いのか情報が見当たらなかったため、まとめました!
大前提:すべての鍵は「海外転出届」を出すか、出さないか
まず、最初にして最大の決断。
それは「海外転出届を出して、住民票を抜くかどうか」です。
ワーホリ(1年以上の海外滞在)の場合、生活の拠点が日本からなくなるため、役所に「海外転出届」を提出するのが原則です。
これによって、あなたは法律上「非居住者」という扱いになります。
結論から言うと、「非居住者になる(=住民票を抜く)」かどうかだけで、税金・年金・保険の支払義務がすべて変わってしまうのです。



「税金・年金・保険で何がどう変わるのか」を一覧にまとめました。
まずは全体像をつかんでください。
| 項目 | 海外転出届を「出す」(非居住者) | 海外転出届を「出さない」(居住者) |
|---|---|---|
| 住民税 | 支払い義務がなくなる(翌年度) | 支払い義務が「継続」 |
| 国民年金 | 支払い義務がなくなる(任意加入は可) | 支払い義務が「継続」 |
| 国民健康保険 | 資格喪失(脱退扱い)(保険料の支払いは停止) | 支払い義務が「継続」 |
住民税に関しては、翌年度という考え方なので詳しくは「【時系列】ワーホリ退職プロジェクト・完全ロードマップ」で具体例を交えて解説します!
あえて「海外転出届を出さない」方が良い人とは?
比較表の通り、「出す」方が金銭的メリットは大きいですが、以下のような人は「出さない」方が良い場合もあります。
「出さない」方が良い可能性がある人
- 滞在期間が1年未満(3ヶ月〜半年)の予定である人
(法律上、1年以上の滞在が「海外転出」の目安です) - 日本の「国民健康保険」をどうしても維持したい人
(持病がある、高額な海外保険に入りたくない、など) - 将来の「年金受給額」を1円も減らしたくない人
(任意加入の手続きが面倒で、そのまま義務として払い続けたい人)
最大のデメリットは?
「出さない」場合、海外にいて使えない保険や年金、住民税(前年度所得分)の支払い義務が続きます。これは30歳会社員の所得だと、年間数十万円の大きな負担になる可能性があります。
【私たちの結論】1年以上のワーホリなら「出す」が最適解
「出さない」メリット(国民健康保険の維持など)もありますが、高い保険料や税金を払い続けるデメリットの方が大きいと私たちは判断しました。
(医療費の不安は、民間の「海外旅行保険」でカバーします)
この記事は、「海外転出届を出す」ことを前提とした、最も金銭的メリットが大きく、法的に安全な手続きの完全ガイドです!
【時系列】ワーホリ退職プロジェクト・完全ロードマップ
ここからが本題です。
SEのプロジェクト管理術で、やるべきことを時系列(フェーズ別)に分解します。
「会社に伝える」最も緊張する時期です。
ここでは円満に退社を迎える準備をします。
- 会社の「就業規則」を確認する
「退職の意思表示は、何ヶ月前までに必要か」を確認(通常1〜2ヶ月前) - 上司や責任者に「退職の意向」を伝える
ここが一番重要なところです。
【採用担当の視点】
退職理由はポジティブに伝えましょう。「海外での経験を通じてキャリアアップしたい」など、会社への不満ではなく「未来」を語るのが円満退社のコツです。
引継ぎを完璧に行う意志も示しましょう。 - 「退職金」の有無と条件を確認する
アラサー会社員である30歳前後の人は、勤続3年以上の方が多いことでしょう。会社によっては退職金制度があったりするので、しっかり確認をしておきましょう。(私の場合はありませんでしたが・・・)


会社への退職申請と、仕事の引継ぎを完璧に行います。
- 退職届を正式に提出する
- 【最重要】会社に「2つの書類」をリクエストする
総務・人事に「退職後に自宅へ郵送してほしい」と必ず伝えます。
1. 離職票:失業保険の延長手続きで使います。
2. 源泉徴収票:確定申告(税金を取り戻す)で使います。 - 引継ぎ資料の作成(社会人としての腕の見せ所)
後任者が困らないよう、ドキュメントや手順書を残します。これがあなたの「信頼」になります。
退職し、まだ住民票がある無職期間です。
この期間に足を運ぶのは、役所です。
1. 役所(市区町村)でやること
会社を辞めた翌日から、会社の保険や年金は使えなくなります。
渡航までの「つなぎ」として、以下の切り替え手続きを行ってください。
- 国民健康保険への切り替え
会社の保険証を返却し、「国民健康保険」に加入します。(※渡航までの数週間〜数ヶ月間、無保険状態を防ぐため必須) - 国民年金への切り替え
厚生年金から「国民年金(第1号被保険者)」への切り替え手続きをします。
※ハローワークでの「失業保険の受給延長申請」について
「失業保険の延長手続きをしなくていいの?」と不安になるかもしれませんが、以下の理由から手続き自体が不要(原則不可)です。
理由:海外にいると「すぐに働ける状態」ではないから(タップして詳細)
多くの人が誤解していますが、ワーホリ(私的な海外渡航)は受給期間延長の「やむを得ない理由」として認められないケースが大半です。(申請自体は可能)
原則:
海外滞在中は受給できず、帰国時点で退職日から1年が経過していると受給期間が過ぎてしまうため、受給権は消滅します。また、帰国が1年以内でも失業状態でないと支給はされないので注意。
対策:
もし受給したい場合は、「渡航前に給付をもらい切る」か「1年以内に帰国して申請する」必要があります。
※例外的に「JICA(青年海外協力隊)等の公的活動」などは認められる場合がありますが、一般的なワーホリは対象外です。
「なぜもらえないのか」「損しないための3つの選択肢」については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。気になる方は併せてご確認ください。


2. 自宅でやること:NISA・401k(企業型DC)の整理
役所の手続きと並行して、自宅で資産の手続きを進めます。
特に「NISA」と「企業型DC(401k)」は、海外へ出る前に確認しておかないと後からトラブルになりやすい領域です。
NISA(一般/つみたて)
ワーホリで海外に出る場合、多くの人が誤解しやすいのがNISA の扱いです。
ポイントは次のとおりです。
- 海外転出(非居住者)になると、NISA口座での新規買付・積立は原則できない
- 現時点で保有している資産はすぐに「現金化(解約)」までする必要はない(課税口座へ移すという選択肢があるため)
- ただし、NISAのまま非課税で継続できるかは証券会社ごとに対応が異なる
- 一般口座へ移管される場合がある
- 非居住者の取扱い自体を受け付けない証券会社もある
- 帰国して国内居住者に戻れば、NISA の買付・積立を再開できる



原則として、非居住者になるとNISAを維持するのは難しいです。
ただ、金融機関ごとに対応が違う場合もあるので、出国前に一度問い合わせてみるのがおすすめです。
以下の記事でも、ワーホリ中のNISAの扱いについて詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。


企業型DC(401k)→ iDeCo(個人型DC)
- 退職すると、企業型DC(401k)は自動的に終了(企業型DC脱退者扱い)
- 退職後6カ月以内に iDeCo(個人型DC)へ資産移換が必要
- 移換しない場合、資産は国民年金基金連合会へ強制移管される
- この場合、年間手数料が発生する
- 自分で運用商品を選べず運用効率が悪くなる
iDeCo口座の開設には時間がかかるため、必ず「渡航前」に移管手続きを完了させましょう!
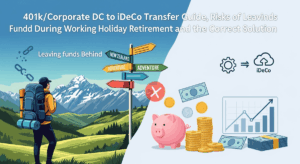
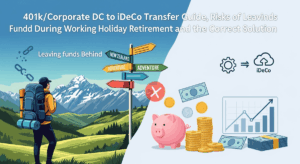
いよいよ住民票を抜きます。
- 役所で「海外転出届」を提出する
渡航日の14日前から可能 - 国民健康保険の「脱退」手続き
海外転出届と同時に行います。保険証を返却し、保険料の精算をします。 - 国民年金の「資格喪失」と「任意加入」の選択
海外転出届と同時に、国民年金の強制加入資格が喪失(停止)します。これにより支払い義務はなくなります。
ただし、この「任意加入しなかった期間(カラ期間)」は、将来もらえる年金額の計算に含まれず、原則として後から追納(後払い)もできません。
もし将来の受給額を減らしたくない場合は、同じ窓口で「任意加入の申出」を行い、海外から保険料(月額 約17,500円 ※年度により異なる)を支払い続ける必要があります。 - 国外転出者向けマイナンバーカードに切り替え
日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになっています。(令和6年5月27日から)海外転出の旨が記載され、戻ってきますので、忘れずにマイナンバーカードの手続きも行いましょう。
【私たちの選択】夫婦で「判断が分かれました」
実はこの問題、私たち夫婦の間でも意見が真っ二つに分かれました。
| 夫(私) | 任意加入しない (手元資金の最大化を優先) |
| 妻 | 任意加入する (将来の安心を優先) |
夫(Kea)の言い分:
「将来の受給額が減るリスクよりも、今の手元資金(ワーホリ資金)を最大化して、現地での経験に投資したい!」
妻(はる)の言い分:
「月1.7万円で将来の減額リスクが消えるなら安いもの。私は絶対にお金を払って安心を買いたい!」
結果として、我が家は「半分はリスクを取り、半分は守りを固める」というリスク分散型になりました。
ご夫婦で行く場合は、必ずしも合わせる必要はありません。
それぞれの価値観で決めるのが一番です。



ワーホリ期間中に、国民年金に任意加入するかどうかはかなり迷いました。生涯に渡っていくら年金額が減るのか試算した記事もありますので、判断の材料にしてもらえると嬉しいです。
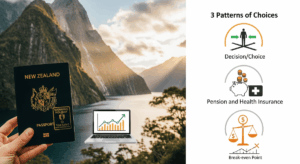
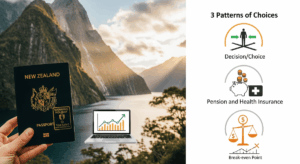
実は、渡航したら全部おしまいというわけではありません。
忘れた頃にやってくる「税金」の手続きが残っています。
1. 住民税(忘れるとヤバイ)
住民税は「前年の所得」に対し「その年の1月1日時点の居住者」に課税されます。
(例)2026年4月に退職・渡航した場合:
- 2026年1月1日には日本にいたため、2026年度の住民税(2025年分の所得に対する税)の支払い義務があります。
- あなたが渡航した後の2026年6月頃、この2025年分の所得に対する納税通知書が、日本で居住していた住所宛に届きます。
2. 確定申告(お金が戻ってくる可能性あり)
退職した年(例:2026年1月〜4月)の給与からは、税金(所得税)が多めに天引き(源泉徴収)されています。
翌年(2027年)の2月〜3月に「確定申告」をすれば、払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性が非常に高いです。
【最重要】2つの税金問題をどう解決するか?
あなたが出国した後、「住民税の納税(2026年6月)」と「所得税の還付申告(2027年3月)」という2つのイベントが発生します。これらをクリアする「合理的な最適解」は1つしかありません。
最適解:「納税管理人」を選任する
渡航前に、親族などに「納税管理人」になってもらう届出を、
- 役所(住民税用)
- 税務署(所得税用)
の両方に出しておきましょう。
納税管理人さえいれば、あなたが海外にいても、
- 2026年6月に届く「住民税」を代理で納付してもらえる
- 2027年3月に「確定申告」を代理で行い、「還付金」を受け取ってもらえる
という、2つの問題を完璧にクリアできます。
参考サイト:
出国前の準備が大切です!海外勤務者の確定申告と納税(税理士法人Right Hand Associates 2025/3/26投稿)
フランスからe-TAXで確定申告をする(yuki | フランスワーホリ日記 2025年3月9日投稿)
(補足)納税管理人を頼める人が誰もいない場合は?(タップして開く)
この場合は非常に困難ですが、以下の2つの対策(どちらも渡航前に手続き必須)を組み合わせる必要があります。
1. 住民税の支払い対策
渡航を6月以降に遅らせ、納税通知書を「自分で」受け取り、全期前納(一括払い)してから出国する。
2. 確定申告(還付)対策
渡航前に税務署に出向き、「e-TaxのID・パスワード方式」の利用登録を済ませておく。(※2024年5月の法改正により海外転出後もマイナンバーカードの継続利用が可能になりましたが、PC環境等のリスクを考えるとID・パスワード方式の併用が安全です)
【私たちの選択】
私たちは「5月退職 → 日本一周 → 7月出国」という特殊なスケジュールです。
そのため、上記「補足」のパターンと同じ流れにしました。
- 住民税の納税通知書(6月)は、日本一周中に受け取り、自分で納付します。
- 所得税の還付申告(翌年)のために、親族に「納税管理人(所得税用)」を依頼しておきます。
もし日本一周などを通知書が届く6月を待たずに出国する方(例:4月渡航)は、最初から「納税管理人」を立てるのが最も合理的です!
ワーホリ準備は「退職」だけではありません。
プロジェクト(退職)と並行して、以下の3大タスクも進めていく必要があります。
- 国際免許証(運転するなら必須)
- VPN(日本の動画を見るなら必須)
- 医療準備(高額請求を防ぐために必須)
それぞれの攻略法を以下の記事にまとめました。
併せてお読みください。




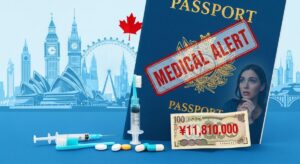
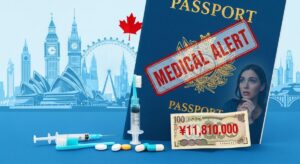
【コラム】住民税(数十万)を合法的に0円にする「1月1日」ルール
「12月に海外転出届を出して年内に渡航すれば、住民税(数十万)が0円になるのでは?」と思った方もいるのではないでしょうか。



めちゃくちゃ鋭い、良い視点です!
住民税の観点だけ見れば、それが一番お得(節税効果が最大)になります。
住民税は、「その年の1月1日」に日本に住所がある人に対して、「前年(1月〜12月)の所得」を元に課税されます。
この「1月1日ルール」で、どれだけ差が出るか見てみましょう。
なぜお得なのか?:2つのパターン比較
パターンA:2025年12月30日に渡航(お得なパターン)
- 2026年1月1日の状況: あなたは日本に住所がない「非居住者」です。
- 2026年度の住民税(2025年分の所得に対する税): 課税されません(0円です)。
- 結果: 2025年に働いて得た所得(例:1月〜11月分の給与)に対する住民税がまるまる非課税になります。
パターンB:2026年1月2日に渡航(損するパターン)
- 2026年1月1日の状況: あなたはまだ日本に住所がある「居住者」です。
- 2026年度の住民税(2025年分の所得に対する税): 全額(1年分)課税されます。
- 結果: あなたは2026年1月2日に出国して日本にいないにもかかわらず、2025年分の所得に対する住民税(通常、2026年6月頃に請求が来る)を全額支払う義務が生じます。
ただし、年内退職が「常に」お得とは限りません!
比較すべき3つのポイント
- 住民税の節約額(例:-40万円)
- ボーナス(夏・冬)の受給額(例:+55万円)
- 年末年始の航空券代(高騰)
例えば、住民税(40万)を節約するためにボーナス(55万)をもらい損ねては、かえって損ですよね。
この「損益分岐点」の計算は、あなたの年収や状況によって異なります。



まさに、この「いつ辞めるのが一番得か?」問題が一番悩ましいですよね。
SEの私が年収別に徹底的にシミュレーションした記事を用意しました。ぜひ、退職タイミングの参考に読んでみてください。


【FAQ】ワーホリ前の退職手続きでの「よくある疑問」
- 結局、ワーホリでの海外転出届(住民票抜き)のデメリットは?
-
A以下の3つが主なデメリットです。
- 国民健康保険が使えない(=海外旅行保険への加入が必須になる)
- 国民年金が「カラ期間」になる(=任意加入しないと将来の受給額が減る)
- 行政サービスが使えない(印鑑証明の発行、マイナンバーカードの電子証明書が使えない ※継続利用手続きを除く)
1年以上のワーホリの場合、これら(特に保険)を日本で払い続ける金銭的デメリットの方が大きいため、「出す(非居住者になる)」が最適解となります。
- ワーホリ(1年)の予定が、半年で帰国したらどうなる?
-
すぐに役所で「転入届」を出せばOKです。
海外転出届を出していても、帰国後に転入届を提出した日から、あなたは再び居住者に戻ります。その日から国民健康保険と国民年金(強制加入)への再加入手続きを行えば問題ありません。
- ワーホリに行くので、失業保険の受給期間を延長できますか?
-
残念ながら、原則できません。
延長が認められるのは「病気、出産、配偶者の海外転勤への同行」などの理由に限られます。自分の意思で行くワーホリは対象外のため、帰国後に受給しようとしても、退職から1年が経過していれば権利は消滅しています。
「もらえる前提」で資金や帰国後の計画を立てないよう注意しましょう。 - NISA/401kの手続きを忘れて出国したらどうなりますか?
-
「大損」するリスクが非常に高いです。
- NISA/iDeCo: 証券会社に「非居住者」であることを申告しないと、口座を「強制解約」され、利益が課税されるリスクがあります。
- 企業型DC(401k): 退職後6ヶ月以内にiDeCoへの移管手続きをしないと、資産が「自動売却(現金化)」され、国民年金基金連合会に手数料を引かれながら塩漬けにされます。
30代会社員にとって、これを見逃すのは致命的です。必ず渡航前に手続きしましょう。
- 納税管理人(親族)がいない場合、確定申告(還付)は諦めるしかない?
-
諦める必要はありませんが、渡航前の準備が必須です。
渡航前に税務署で「e-TaxのID・パスワード方式」の利用登録を済ませておきましょう。これがあれば、海外からでも(マイナンバーカードがなくても)PCやスマホで還付申告が可能です。
まとめ:退職・ワーホリ手続きの完全ToDoリスト
最後に、「最終チェックリスト」をまとめます。
- (退職3ヶ月前)上司に退職意向を伝え、円満退社を目指す
- (退職1ヶ月前)会社(人事/総務)に「離職票」「源泉徴収票」の郵送を依頼する
- (退職直後)市役所/区役所で、「国民健康保険」「国民年金」に加入する(渡航までのつなぎ)
- (渡航前)証券会社/銀行に連絡し、「NISA/iDeCo」の非居住者手続きをする
- (渡航前)金融機関で「企業型DC(401k)」をiDeCoに移管する
- (渡航前)「納税管理人」の届出を「2箇所」で行う
・市役所/区役所で「住民税」の納税管理人を届出
・税務署で「所得税(確定申告)」の納税管理人を届出 - (渡航14日前〜当日)市役所/区役所で、以下の手続きを「同時に」行う
1. 海外転出届の提出
2. 国民健康保険の脱退(と保険料の精算)
3. 国民年金の資格喪失(または任意加入の選択)
4. マイナンバーカードの国外継続利用の手続き
5. (住民税の)納税管理人の届出 - (渡航後・翌年)納税管理人に税務署で「確定申告」をしてもらい、税金還付を受ける
一見複雑ですが、時系列でプロジェクトとして管理すれば何も怖くありません。
この記事が、あなたの30歳からのワーホリ挑戦の完璧な攻略ログになることを願っています!


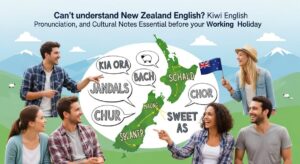
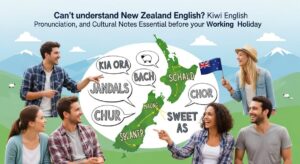


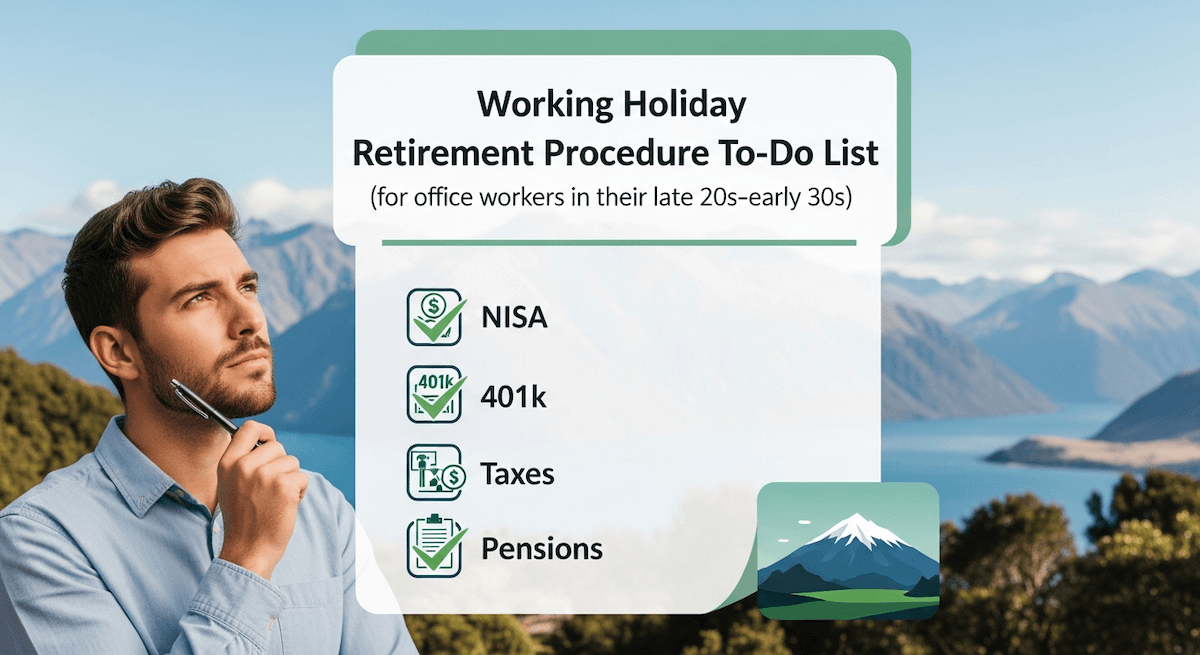
コメント